年末に来年のカレンダーを見ると、GW を何連休にできるかが気になってしまいますね。
5月5日のこどもの日は端午の節句と言うことで、小さい頃にお祝いをしてもらった経験から印象が強いと思います。ところが5月3日の憲法記念日って、あんまり意識したことないかもしれません。
憲法記念日って、どういう由来で決まったのでしょうか?
調べてみましたのでご覧ください。
スポンサーリンク
国の成長を期待する日
社会科の公民の時間で習ったように、太平洋戦争の敗戦によって、GHQ の指導により、日本は軍国主義から平和主義へと国の方針を転換することになりました。
その過程で新憲法(日本国憲法)が制定され、1947年5月3日に施行、つまり「この日から日本国憲法の下で国を運営しますよ」と決められました。
祝日について決められている「祝日法」には、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」とあり、翌1948年から憲法記念日として祝日になっています。
文化の日と関係がある?
憲法の限らず法律とは、施行する前、つまり効力を発揮する前に国民に対し、「こういう法律を定めました」と知らせる手続きがあります。
これを「公布」といいます。
日本国憲法は、前の大日本帝国憲法(明治憲法)からの改正という手続きを経て、施行日の半年前になる 1946年11月3日に公布されました。
ここで、11月3日って、今なら文化の日ですよね?
ところが、11月3日は明治天皇の誕生日で、当時は明治節という祝日になっていました。
いま、4月29日は昭和の日ですが、少し前は「みどりの日」と呼ばれ、もっと前は昭和天皇の誕生日として祝日でした。(今は12月23日が天皇誕生日ですね)
ある説によると、明治節を違う意味での祝日にするために逆算して、11月3日の公布、その半年後に施行したと言われています。
そして、11月3日は憲法が平和と文化を重視していることから文化の日となりました。
【関連記事】

憲法の三大要素とは?
社会科の授業みたいですけど、日本国憲法の三大要素 (筆者が中学のときの先生は「日本国憲法の目玉商品」と呼んでいました(笑 ) について振り返ってみましょう。
戦前は天皇が主権者で、国の方針を最終的に決める権力を持っていました。国民の権利は一応保障されていましたが、政府の意向でいくらでも制限をつけることができました。
その結果、軍国主義への道を歩むことで、国土は焦土となり、多くの犠牲を払いました。
そこで、GHQ の監督の下(…と書くといろいろ微妙ですが) 「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という三大要素を盛り込みました。
天皇制をなんとしても残したかった日本側は、「戦争放棄」を入れることで GHQ と取引した
…という説がありますが、ここでは深入りしません(^^ゞ
憲法改正とか、解釈改憲といった議論がありますけど、GW のまっただ中、憲法について考えてみるのもいいかもしれませんね。
スポンサーリンク

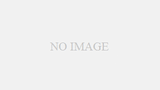

コメント