GW が終わり、連休気分も一段落。五月病にもなんとか罹らずにクリアして、ひと月経つと今度はジメジメした梅雨のシーズンがやってきます。
本州では6月ですが、沖縄ではGW が終わったらもう梅雨ですね。
梅雨になったら、一ヶ月半ほどしとしとと雨が降って、傘が手放せません。
そもそも、なんで梅雨ってあるんでしょうか?
北海道に梅雨がないのはなぜ?
このあたりの疑問に注目して調べてみたいと思います。よかったらお付き合いください。
スポンサーリンク
なぜ梅雨が起こるの?
梅雨の時期には、日本の北にはオホーツク海気団、南には小笠原気団という高気圧の塊(気団)がやってきます。
オホーツク海気団は、名前の通り、オホーツク海にある冷たく湿った気団で、小笠原気団は高温多湿の気団です。
冬にはオホーツク海気団が強く、夏には小笠原気団が強くなります。
「強い」というのは、大きくなる(発達する)という意味ですね。
冬が終わり、春になり、初夏になると冷たいオホーツク海気団は南から来る暖かい小笠原気団によって北に追いやられます。
そして、2つの気団の境目が日本列島にかかります。暖かい空気と冷たい空気がぶつかると、冷たい空気が暖かい空気の下に入り込みます。
ここで上昇気流が起こります。上昇気流が起こると雲ができます。雲が寒気で冷やされると、雲として水分を保持できなくなり、雨となって降ってきます。
これが梅雨前線です。
▽国土交通省 北陸地方整備局 の画像から

普通の低気圧だと、日本列島上空を西から東に向かって流れる偏西風に乗って低気圧も移動していくのですが、オホーツク海気団と小笠原気団が日本列島上でガチンコ勝負をしているために前線が留まっています。
だから、梅雨前線を停滞前線とも言います。
梅雨入り、梅雨明けはいつ頃?
気象庁のホームページによると、梅雨入り、梅雨明けの平年値が載っています。
沖縄:5月9日頃 ⇒ 6月23日頃
九州南部:5月31日頃 ⇒ 7月14日頃
九州北部:6月5日頃 ⇒ 7月19日頃
四国:6月5日頃 ⇒ 7月18日頃
中国:6月7日頃 ⇒ 7月21日頃
近畿・東海:6月8日頃 ⇒ 7月21日頃
関東甲信:6月8日頃 ⇒ 7月21日頃
北陸:6月12日頃 ⇒ 7月24日頃
東北南部:6月12日頃 ⇒ 7月25日頃
東北北部:6月14日頃 ⇒ 7月28日頃
北海道には梅雨がありません。
「蝦夷梅雨」(えぞつゆ)と呼ばれる2週間程度の雨の期間がありますが、気象庁は梅雨と認めていません。
【関連記事】




2014年の梅雨入り、梅雨明けは?
南から梅雨が明けていくのは、小笠原気団が真夏に向かって発達していくからです。
小笠原気団がどんどん発達して、オホーツク海気団を北に追いやっていくことで、南から梅雨が明けていきます。
津軽海峡より北に追いやったら、全国で梅雨が明けることになりますね。
…ということは、オホーツク海気団と小笠原気団のパワーバランスで梅雨入り、梅雨明けの時期が決まります。
2014年は5年ぶりにエルニーニョ現象が発生すると言われ、そうなると寒気が強く、暖気が弱くなります。
オホーツク海気団を追いやるのが遅れるのではないかと言われていますので、今年の梅雨入り、梅雨明けは平年より遅れそうです。
スポンサーリンク

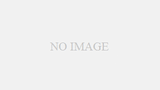

コメント